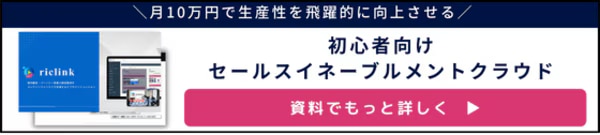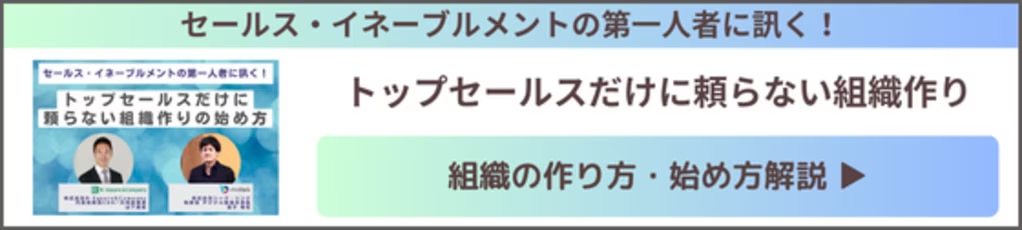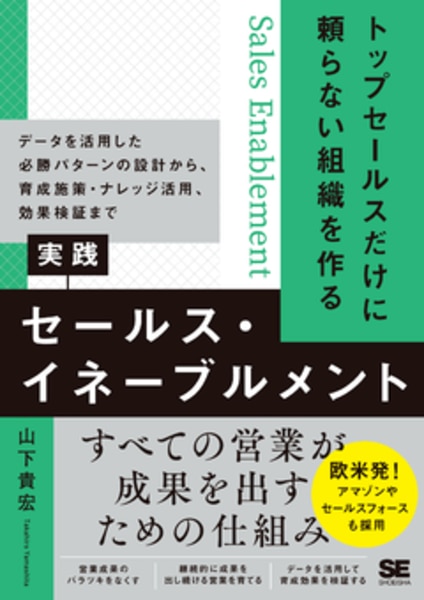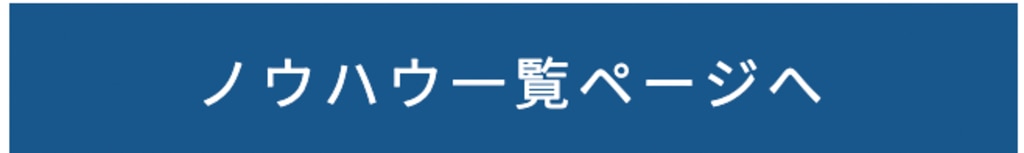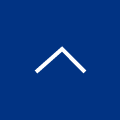セールス・イネーブルメントとは?注目される理由・実施のポイントなど総まとめ
セールス・イネーブルメントとは、「営業が成果を出せるようにする取り組み」のことを指す言葉です。
本記事では、このセールス・イネーブルメントの概要や注目されるようになった理由、取り組み方などをお伝えします。
なお、シーズ・リンクでは、セールス・イネーブルメントを支援するツール「riclink(リクリンク)」を提供しています。
riclinkの機能や活用方法の詳細については、下記から資料を無料ダウンロードのうえご確認ください。
目次[非表示]
- 1.セールス・イネーブルメントとは?
- 2.セールス・イネーブルメントが注目される5つの理由
- 2.1.理由1. 商品・サービスの変化
- 2.2.理由2. 人材の変化
- 2.3.理由3. 働き方の変化
- 2.4.理由4. 顧客の変化
- 2.5.理由5. マーケティングの変化
- 3.セールス・イネーブルメントに取り組む流れ5ステップ
- 3.1.ステップ1. 知識・ノウハウを収集する
- 3.2.ステップ2. 専任の担当者を配置する
- 3.3.ステップ3. 施策を実施する
- 3.3.1.営業スキルの向上
- 3.3.2.営業プロセスの標準化
- 3.3.3.営業コンテンツの作成・整理
- 3.4.ステップ4. 施策の成果を分析する
- 3.5.ステップ5. 施策を改善する
- 4.セールス・イネーブルメントで得られる4つのメリット
- 5.セールス・イネーブルメントに取り組む際の2つのポイント
- 6.セールス・イネーブルメントに成功した事例
- 7.セールス・イネーブルメントでよくある2つのQ&A
- 8.「riclink」でセールス・イネーブルメントを成功させよう!
セールス・イネーブルメントとは?

セールス・イネーブルメントは、「営業」を指すSalesと、「有効化」という意味のEnablementを組み合わせた言葉で、簡単にいうと「企業の営業活動を強化する取り組み」のことを指します。
「営業担当の成長を通じて、成果をあげること」がコンセプトで、取り組む上では、期待される「成果」を起点に求められる「行動」と「知識・スキル」をつなぐ意識が大切です。
そこで、まずは「自社の営業では、どういった成果が求められるか?」を考えてみてください。
そのうえで、「成果につながる行動は何か?」「行動に必要なスキル・知識は何か?」と、順番に洗い出していくとセールス・イネーブルメントは成功しやすくなります。
セールス・イネーブルメントの具体的な内容
セールス・イネーブルメントでは、下記3つの領域に取り組むことになります。
|
まず1つ目は、「営業担当者のスキルアップ」です。
この領域では、社内の営業担当の能力を引き上げることで、売上の向上を目指します。
具体的には、「営業に必要なスキルの洗い出し」と「個々の営業担当の現状の把握」をした上で、不足しているスキルは研修などによって強化していくことになります。
2つ目は、「営業プロセスの標準化」です。
営業活動の流れや手法は、担当者によって異なるケースが意外と多いものです。
そこで、「最も成果が出やすい営業プロセス」を確立し、営業部門で共有するのが、この領域の狙いになります。
これに取り組むことで、担当による成果のバラつきの抑制を期待できます。
最後の領域は、「営業コンテンツの作成・整理」です。営業活動では、担当者が下記のような資料を作成し、お客様へ提供します。
|
しかし、これらを担当者が別々に作成してしまうと、品質にバラつきが生まれかねません。
また、それぞれの資料を毎回ゼロから作成するのは、非常に効率が悪いです。
そこで、「統一の資料」や「資料のテンプレート」を作成して営業部門で共有することで、品質のバラつきがなくなり、作成する際の効率もアップすることが見込めます。
セールス・イネーブルメントと「従来の人材育成」の違い
セールス・イネーブルメントは、従来から行われてきた「営業担当の人材育成」とよく混合されます。
両者のうち、まず「従来の人材育成」は、前述の「3つのセールス・イネーブルメントの領域」のうち、「営業担当者のスキルアップ」のみに焦点が当てられます。
一方で、セールス・イネーブルメントは、「営業プロセスの標準化」と「営業コンテンツの作成・整理」にも同時に取り組むことが特徴です。
こうして営業活動を「総合的」に改善することで、セールス・イネーブルメントでは、より高い成果が期待できます。
セールス・イネーブルメントが注目される5つの理由

近年、セールス・イネーブルメントが注目されている理由は、下記5つの変化が起きたからだと考えられます。
|
ここでは、それぞれの項目について詳しく見ていきます。
理由1. 商品・サービスの変化
近年、顧客のニーズが多様化したことによって、同じ商品・サービスでも複数のタイプやオプションを選べるケースが多く見られます。
例えばシャンプーの場合、同じブランドでも、髪のお悩みによって
- パサつきをなくす
- うねりを解消する
- 頭皮をケアする
など、複数のタイプが販売されることが多いです。
また、営業支援ツールの場合は
- 利用できる機能
- ログインできるアカウント数
- 管理できるファイルの容量
などに応じて、いくつかのプランが用意されます。
このようにして、自社の扱う商品・サービスの種類が増えれば増えるほど、営業担当がすべてを把握するのが難しくなってしまいます。
そこで、セールス・イネーブルメントの一環として「商品に関する勉強会」を開いたり、「サービス概要の資料」を作成したりして情報共有をする企業が出てきました。
理由2. 人材の変化
日本では少子高齢化によって、優秀な若手を採用することが年々難しくなってきています。
このため、営業組織の強化を「新規採用」ではなく「今いる社員のスキルアップ」で補おうとする企業が増えてきました。
そこで、営業強化の手法の1つとして「セールス・イネーブルメント」に注目が集まっています。
理由3. 働き方の変化
一昔前は、「残業や休日出勤をして、時間をかけることで成果をあげる」という考え方をする方も多くいました。
しかし、近年は「働き方改革」に見られるように、できるだけ労働時間を短くしようとする動きがあります。
そこで、短時間で大きな成果をあげるために、セールス・イネーブルメントに取り組んで営業を効率化しようとする企業が増えています。
理由4. 顧客の変化
インターネットの普及によって、商品・サービスの「概要」くらいであれば、誰でも簡単に調べられるようになりました。
このため商談する相手は、すでに自社の商品・サービスについては大体わかっているケースが多いです。
そこで、営業担当には
- どうして、その商品が必要なのか?
- どのように商品を使えばいいのか?
- 使うことで、どれほどの成果が見込めるのか?
などを、相手へ的確に伝えることが求められるようになっています。
そのためには、「商品・サービスに関する深い知識」や「他社の成功事例」などを営業部門で共有しておくことが有効であり、この「情報共有」もセールス・イネーブルメントで取り組まれる施策の1つです。
理由5. マーケティングの変化
マーケティングに関するツールやサービスが発達したことで、以前よりも効率的にリード(見込み顧客)を獲得できるようになりました。
しかし、大量のリードを獲得しても、営業部門のリソース不足で、すべてにアプローチできていない企業は多いです。
そこで、機会損失を減らすために、セールス・イネーブルメントに取り組んで、営業を効率化しようとする企業が増えてきました。
セールス・イネーブルメントに取り組む流れ5ステップ

実際にセールス・イネーブルメントに取り組む際の流れは、下記のとおりです。
|
それぞれのステップについて、詳しく見ていきましょう。
ステップ1. 知識・ノウハウを収集する
まずは、セールス・イネーブルメントに関する知識やノウハウを収集します。
今ご覧いただいているようにWeb記事を読んだり、関連書籍を購入したりして、セールス・イネーブルメントの基礎知識を身に付けましょう。
おすすめのセミナー・書籍については、後述の「セールスイネーブルメントが学べるセミナー・本はある?」という見出しのなかで紹介します。
ステップ2. 専任の担当者を配置する
企業として、本格的にセールス・イネーブルメントに取り組むのであれば、専門の部署を作って担当者を配置するのがおすすめです。
これは、セールス・イネーブルメントでは営業活動を幅広く改善するので“やるべきこと”が多く、「兼任」では手が回らなくなる恐れがあるからです。
もし、社内にセールス・イネーブルメントのノウハウを持ったスタッフがいなかったり、リソースが足りなかったりした場合には、「担当者の新規採用」や「外部へのコンサルティング依頼」も検討してみてください。
ただし、「新規採用」も「外注」も比較的高いコストがかかってしまいます。
そこでおすすめなのは、セールス・イネーブルメントのための「ツール」を導入することです。
ツールを入れると、それを提供している企業のカスタマーサクセスからのサポートを受けられます。
これによって、社内にセールス・イネーブルメントのノウハウがなくても、ツールを提供する企業と二人三脚で取り組めます。
ステップ3. 施策を実施する
専門の部署を設置したら、下記3つのセールス・イネーブルメントの施策に着手します。
|
それぞれで具体的に何をするのか、見ていきましょう。
営業スキルの向上
社内の営業スキルを向上させるためには、まず「必要なスキルの洗い出し」をします。
その際は、営業部門で活躍している社員からヒアリングをすると良いです。
スキルの洗い出しができたら、続いては営業担当者それぞれの「現状のスキル」を把握します。
ここではアンケートを取ったり、管理職にヒアリングしたりして、なるべく正確に把握することを目指してください。
最後に、「必要なスキル」と「担当者の現状」を見比べ、不足しているスキルを研修によって強化していきます。
営業プロセスの標準化
「営業プロセスの標準化」とは、もっとも成果の出やすい営業活動の流れを確立することです。
この標準化にあたっても、まずは結果を出している社員にヒアリングすることをおすすめします。
また、マーケティング部門と連携して、下記のそれぞれのフェーズで「何をするのか」を整理することも大事です。
|
そうして「最も成果が出やすい営業プロセス」がまとまったら、マニュアル化を進めます。
完成したマニュアルは営業部門で共有し、必要に応じて研究会を開くことで、標準化した営業プロセスを社内に浸透させてましょう。
営業コンテンツの作成・整理
「営業コンテンツの作成・整理」では、まず既存のコンテンツを一箇所にまとめて「使うシチュエーション」ごとに整理します。
そして、標準化された営業プロセスを見ながら、それぞれのフェーズで必要になるコンテンツを検討し、不足しているものがあれば新しく作成しましょう。
このとき、社内にリソースが不足している場合には、コンテンツの制作を外注するのも一手です。
弊社も制作代行サービスを提供していますので、ご興味があれば下記からお気軽にお問い合わせください。
>>>「コンテンツサブスクプラン」について詳しく聞いてみる<<<
ステップ4. 施策の成果を分析する
施策を実施したら、必ず「成果」の分析をしましょう。その際に見るべき項目の例は、下記のとおりです。
|
ステップ5. 施策を改善する
最後のステップは、分析した結果を踏まえて「施策を改善する」ことです。
例えば、商談相手の業界ごとの「受注率」をチェックした際、ほかと比べて著しく数字が悪い業界があったとします。
低迷の原因を調べた結果、「コンテンツ不足」が露呈したら、新しく制作することで受注率を改善できます。
他方、「受注率の低い業界」からは手を引いてしまい、「受注率の高い業界」に集中して売上を伸ばしていくのも一手です。
以上のように、「より高い成果を上げるためには、どのような取り組みが有効か?」を考え、次の施策に活かすことが大切です。
セールス・イネーブルメントで得られる4つのメリット
セールス・イネーブルメントに取り組むことで、下記4つのメリットが得られます。
|
ここでは、それぞれについて詳しく見ていきます。
メリット1. 担当者ごとの成果の差がなくなる
営業活動は、担当者がそれぞれ「自己流」の方法で行っているケースも多いです。
その場合、担当者によって成果にバラつきが出てしまいかねません。
この点、セールス・イネーブルメントでは「営業プロセスの標準化」や「コンテンツの共有」によって、すべての担当者が同じような営業活動をできるようになります。
これによって、「担当者ごとの成果の差が少なくなる」ことが期待できます。
さらに、「特定の人にしかできなかった仕事」も、営業プロセスの標準化によってマニュアル化されるため、いわゆる「業務の属人化」が解消され、「担当者が離職した際のリスクが減る」ことも大きなメリットです。
メリット2. 営業活動が効率的になる
セールス・イネーブルメントでは、「営業コンテンツの作成・整理」が行われます。
これによって、例えば「提案書」を作成する場合には、あらかじめ用意されているテンプレートに記入するだけで完成するようになります。
こうして、ゼロから作る場合と比べて作業時間が大幅に短縮され、営業活動が効率的になるのは、セールス・イネーブルメントに取り組むメリットの1つです。
また、コンテンツを一箇所にまとめて「使うシチュエーション」ごとに整理しておけば、「必要な資料を探す時間」も少なくなって、より業務が効率化します。
メリット3. 人材育成がしやすくなる
セールス・イネーブルメントの一環として、営業担当に必要なスキルを整理することで「どのように育成すれば良いかが明確になる」こともメリットです。
そのうえで、必要なスキルを伸ばすための研修プログラムを組むことで、新規採用や異動で新しく営業部門に入ってきた社員を着実に成長させられます。
さらに、研修プログラムが確立してきたら研修会を動画にすることで「講師」側の負担が減り、「受講者」としても、いつでもどこでも視聴できるようになります。
メリット4. 営業活動のデータが蓄積される
セールス・イネーブルメントに取り組むと、ツールを活用しながら
- 顧客の情報
- 担当者の情報
- 商談の履歴
などを整理することになります。
これらは、営業活動の現状を分析する際の貴重なデータです。
こうして集まったデータから現状を分析し、次の施策に反映することで更なる成果の向上が期待できます。
セールス・イネーブルメントに取り組む際の2つのポイント

セールス・イネーブルメントに取り組む際のポイントは、下記の2つです。
|
それぞれ詳しく見ていきましょう。
ポイント1. 営業部門と他部署で連携する
セールス・イネーブルメントは、営業部門だけで取り組むのではなく、社内の他部署との連携が必要です。
まず、営業プロセスを標準化するにあたっては「マーケティング部門」との調整が欠かせません。
マーケティング部門は、見込み顧客(リード)を獲得し、購買意欲を高めた上で商談に進む方を選別して営業部門に引き渡してくれています。
そこで営業部門としては、マーケティング部門が顧客にどのようなアプローチをしてきたのかを把握しておくべきです。
そのうえで、営業プロセスを検討することで相手に提供する情報の「漏れ」や「重複」がなくなり、スムーズに成約につなげられます。
また、セールス・イネーブルメントのためのツールを導入する際は「IT部門」との調整も必要です。
「ツールに使える予算の折衝」はもちろん、「ツールで扱う個人情報の管理」についても確認しておかなければなりません。
ポイント2. 便利なツールを導入する
セールス・イネーブルメントでは、下記のような情報を管理することになります。
|
大量のデータを扱うことになるため、専門のツールを使うと管理がしやすいです。
弊社が提供する「riclink」も営業に使うコンテンツを管理できるツールなので、ご興味があれば下記の資料をご覧ください。
セールス・イネーブルメントに成功した事例

株式会社Hajimari様は、「人材マッチングサービス」や「研修・人材育成」の事業を展開している企業です。
同社では、これまで商談のためのコンテンツを多数制作してきましたが、うまく管理できていなかったことが課題でした。
そこで「riclink」を導入し、「ルーム機能」を使って、コンテンツを「目的別・部門別」などのカテゴリにまとめることで、「どのファイルがどこにあるのか」が一目瞭然となりました。
▼「ルーム機能」でコンテンツをまとめるイメージ

また同社では、各コンテンツの閲覧ログを集計しています。
「利用頻度の低いコンテンツ」があれば、「使い勝手の悪さ」や「不足している情報」を検討した上で、使いやすいコンテンツになるよう修正しているそうです。
この事例について詳しく知りたい方は、下記の記事も併せてご覧ください。
また、その他の成功事例も見たい方は、下記の記事をチェックしてみてください。
セールス・イネーブルメントでよくある2つのQ&A

最後に、セールス・イネーブルメントに関して「よくある質問」にお答えします。
Q1. セールス・イネーブルメントが学べるセミナー・本はある?
セールス・イネーブルメントが学べるセミナーとしては、下記の「セールス・イネーブルメント第一人者に訊く!トップセールスだけに頼らない組織作りの始め方」をおすすめします。
このセミナーでは、セールス・イネーブルメントの専門会社を経営する山下貴宏氏に、現場で役立つノウハウを伺いました。
また、おすすめの書籍は、その山下氏が執筆した『トップセールスだけに頼らない組織を作る実践セールス・イネーブルメント』です。
これからセールス・イネーブルメントに取り組もうと考えている方は、まずはこの本から読んでみてください。
Q2. セールス・イネーブルメントに効果的なツールは?
セールス・イネーブルメントに効果的なツールとしては、次のものが挙げられます。
種類 |
概要 |
例 |
|---|---|---|
営業活動支援ツール |
営業活動を効果的・効率的に行うツール |
・SFA |
営業コンテンツ作成・管理ツール |
営業資料の作成を効率化・共同管理するツール |
・CMS |
オンライン商談ツール |
オンライン営業を効果的・効率的に行うツール |
・Web会議システム |
それぞれのツールの詳細は、下記の記事でお伝えしていますので、ご興味があれば併せてご覧ください。
【2021年最新】セールス・イネーブルメントに効果的なツール8選!
「riclink」でセールス・イネーブルメントを成功させよう!

本記事では、セールス・イネーブルメントの概要や注目される理由、取り組み方などを紹介しました。
これからセールス・イネーブルメントに力を入れようと考えている企業に、ぜひおすすめしたいのが、弊社の提供する「riclink(リクリンク)」というツールです。
riclinkでは、散らばった営業資料や動画、ナレッジの管理を1つのクラウド上に集約することで、営業フェーズや顧客層に沿った最適なコンテンツを誰でも使える環境を整えられるため、仕組みで属人化を脱却することができます。
初心者でも使える操作感と更新などの運用性を考えたシンプルな機能で、今まで個々人の経験やスキルに頼っていた「営業の質」を標準化することを強力に支援します。
このriclinkにご興味のある方は、ぜひ下記の資料をご覧ください。
個々人の経験やスキルに頼っていた「コンテンツ活用の仕組み化」を向上することができます。
さらに、ルームは1つのURLで簡単に社外へ共有することも可能なので、顧客へ送付するコンテンツを仕組み化し、営業の質を標準化することがます。